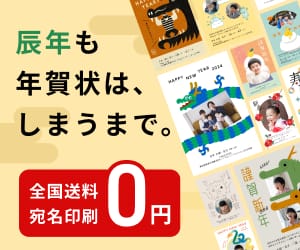喪中の年賀状のマナー。喪中はいつまで?喪中はがきを送る範囲はどこまで?
公開日:2019年11月12日
更新日:2023年12月19日
このページのコンテンツ
年末が近づくと、その年に親族に不幸があった場合、年賀状を出してよいのかどうか迷ってしまう方も少なくないでしょう。喪中はがきのマナーは確立されていないため、絶対にこうしなくてはいけないといった決まりはありません。しかし、一般的なマナーを守るなら、喪中の範囲次第で新年の挨拶を控えた方がよいでしょう。ここでは、忙しいなかでも迷わず喪中はがきを送れるよう、基本的なマナーをご紹介します。

喪中とは
喪中とは近親者が亡くなった際、遺族・親族が故人を偲ぶ期間のことです。「喪」というのは近親者などの身近な方・親しい方の死を悲しみ、冥福を祈りながら身を慎むという意味があり、そのような行動を「喪に服す」といいます。
喪中と混同しやすい言葉として、「忌中」という言葉をご存知でしょうか。いずれも近親者が亡くなった際に身を慎む期間を指しますが、喪中は長くて13ヵ月とされているのに対し、忌中は亡くなってから49日間です。
喪中の期間は故人の死を弔うことを重視するため、お正月料理や年賀状、初詣などといったお正月行事をはじめ、慶事やお祝いごと・派手な行動は控えるのが一般的です。
喪中の範囲
近親者が亡くなった際、何親等の親族が喪中になるのか意外と知らないという方も少なくないでしょう。一般的には「亡くなった方の2親等以内の親族」が範囲になります。
・1親等:父母・配偶者・子
・2親等:祖父母・兄弟姉妹・孫
故人からみた1親等・2親等の親族が一定期間喪中になりますが、近年では2親等以内であっても同居しているかなどで判断する場合もあります。
曾祖父母や叔父叔母、伯父伯母などは3親等に当たるので、喪中の範囲に含みません。
ただし、3親等以上でも故人と同居していたり、または親しい間柄だった場合は喪に服すこともあります。喪中となると避けるべき行動や行事も多々ありますので、この機会にぜひ把握しておきましょう。
喪中の期間
喪中の期間は、続柄によって異なります。まず、1親等となる自分の父母、結婚している場合は義父母の喪中期間は12ヵ月から13ヵ月、自分の子どもも12ヵ月から13ヵ月とされています。
2親等である兄弟姉妹は3ヵ月から6ヵ月、自分の祖父母、配偶者の祖父母は3ヵ月から6ヵ月とされています。曾祖父母と叔父叔母、甥姪は3親等にあたるため喪中期間はありません。
喪中期間に数ヵ月の差があるのは、故人との付き合いによっても喪中期間が変わるからです。たとえば2親等の祖父母の場合、住んでいるところが遠く離れていてほとんど会ったことがないということもあるでしょう。ほぼ面識がない故人に対し6ヵ月も喪に服すというのは現実的ではありません。最近は別居しているというだけで喪中にしない場合もあり、各家庭で喪に服す期間の尺度は異なります。
また、自分の子どもは12ヵ月から13ヵ月となっていますが、配偶者と子どもに関しては決まった喪中期間はないというのが一般的な考え方となっているようです。ただし、この期間というのはあくまでも一般的な基準でしかありません。故人を悼む気持ちに期間はありませんし、故人との関係性や親密度によっても悲しみの深さは違います。
ここで基準となっている喪に服す期間は、あくまでも喪中に控えなくてはいけないことや、喪中にやらなくてはいけないことをするための期間の目安でしかないのです。
喪中はがきとは
喪中の期間はお正月行事など慶事は控えるのが一般的ですが、それは年賀状も同じです。喪中はがきとは、年賀状の代わりとなる年賀欠礼の挨拶状です。
「身内に不幸があったため、年賀状など新年の挨拶は控えさせていただきます」と相手に伝えることが喪中はがきの目的といえるでしょう。
喪中の期間はおおよそ1年間です。近親者が亡くなり喪に服している間、お正月を迎えることになります。その際は、お正月を迎える前に喪中はがきが相手に届くよう、早めに準備をしましょう。
親族に不幸があった場合、喪中はがきを出す親族の範囲
喪中期間の目安が決まっているのは2親等までで、3親等と4親等は特に喪中期間はありません。そのため、喪中はがきを出す親等の範囲は2親等までというのが一般的です。
つまり、配偶者と父母、義父母、子ども(子どもの配偶者)、祖父母、兄弟姉妹、孫に不幸があった場合は喪中はがきを出します。ただし、これはあくまでも一般的な基準であり、必ず喪中はがきを出さなくてはいけないということではありません。
前述したように、疎遠になっていた祖父母や交流のない兄弟姉妹など、喪に服さない場合は出さなくても大丈夫です。逆に、頻繁に交流がある従兄弟や叔父叔母、孫のように可愛がっていた姪っ子や甥っ子であれば、親等に関わらず喪中とする人もいます。
喪に服すというのは、ある程度決まりはあるものの、本来は自分の気持ちで行うことです。もちろん親族というくくりはありますが、何親等であっても、自分の身内が亡くなり深い悲しみの中で新年を祝う気持ちに憂いがあるのであれば、喪中はがきを出してもおかしくはありません。
喪中はがきは誰に出す?
喪中はがきは前述した通り「身内に不幸があったため、新年の挨拶は控えさせていただきます」と相手に伝えるための欠礼状です。
喪中はがきを送る範囲は、送る相手と故人との関係や、疎遠になっているかどうかなどで決まりますが、基本となるのは「年賀状のやりとりをしている人」「葬儀に参列していただいた人」です。
本来、年賀状のやりとりをしている場合は、仕事関係者にも喪中はがきを出します。しかし最近では、プライベートで接点のない仕事関係者には、喪中はがきを送らず、通常通り年賀状を送るケースもあるようです。故人との関わりや間柄によって判断すべきなので、家族と相談の上決定すると良いでしょう。
あくまで「喪中につき、新年の挨拶は控えます」という趣旨を相手に知らせるためのものなので、年賀状のやりとりがない人には送る必要がありません。ただし、故人がお世話になっていた・訃報を知らせるべき相手の場合は喪中はがきを出しても良いでしょう。
葬儀に参列していた人は、もちろん訃報を知っているので喪中はがきを送らなくてもいいのではと考えるかもしれません。
喪中はがきは訃報を知らせるものではなく、あくまで新年の挨拶は控えるということを相手に知らせるもの。参列していただいた方々にもきちんと送るのがマナーです。
また、送る相手が喪中の場合にも喪中はがきは送る必要がありますが、お互い喪中である親族の場合には省略しても良いでしょう。
喪中はがきの基本マナー
冠婚葬祭にそれぞれマナーがあるように、喪中はがきにも基本的なマナーが存在しています。年賀状のように毎年送るようなものでもないので、実は詳しくは知らないという方も少なくありません。
はじめて喪中はがきを出す方はもちろん、今まで出したことがある方もあらためて基本的なマナー・ルールはおさえておきましょう。
喪中はがきの構成
喪中はがきは一般的に「5つの構成」から成り立っています。
(1)喪中につき年賀欠礼の挨拶
(2)故人の名前・亡くなった月・享年、差出人から見た続柄
(3)送り相手への感謝の言葉
(4)結びの挨拶
(5)日付、差出人の住所・氏名
喪中はがきは縦書きが基本です。儀礼的な挨拶状には行頭は下げず、句読点は不要という慣習があり、この場合も例外ではありません。改行やスペースをうまく活用しましょう。
故人の年齢は基本的には数え年で表記します。数え年は、生まれた時点で1歳とし、1月1日の元旦を迎えるたびに1歳ずつ増えていく数え方です。ただし近年は数え年にこだわらず、満年齢で表記する方もいます。
故人の続柄は差出人から見た続柄で記載しましょう。夫婦連名で喪中はがきを出す場合は、夫から見た故人の続柄にします。差出人は夫・妻の順にし、子どもの名前は記載しません。
喪中はがきの文例
先ほど解説した喪中はがきの構成を踏まえて、喪中はがきの文例を2つご紹介します。
喪中につき年末年始のご挨拶をご遠慮申し上げます
本年○月○日に○○(続柄)○○(故人の名前)が○○歳で永眠いたしました
生前に賜りましたご厚情に心から御礼申し上げますとともに
明年も変わらぬご厚誼のほどお願い申し上げます
令和○年○月
(差出人の住所・氏名)
喪中のため新年のご挨拶は失礼させていただきます
本年○月○日に○○(続柄)○○(故人の名前)が○○歳にて永眠いたしました
平素のご芳情を厚くお礼申し上げます
明年も変わらぬご厚誼をお願い申し上げます
令和○年○月
(差出人の住所・氏名)
11月中旬から12月初旬までに届くようにする
喪中はがきは「身内に不幸があったため、新年のご挨拶は控えさせていただきます」という意味で、年賀状のやりとりはできないという旨を伝えるために送るものです。そのため、いつも年賀状をやりとりしている方に迷惑がかからないように、年賀状の準備を始める11月の中旬から12月の初旬までに届くようにするのが基本です。
年賀状の受け付けは通常12月15日から始まるので、喪中はがきを送るのが遅いとすでに投函されてしまうかもしれません。そうなると相手の方にもご迷惑をかけてしまうので、最低でも12月初旬まで、できれば年賀状作成をする前に届くよう11月中旬に送るのが理想的です。
お祝いごとや近況報告は避ける
喪中はがきを書く際にも注意点があります。それは「お祝いごとや近況報告など喪中に関係のない内容は避ける」ということです。喪中はがきは、そもそも年賀状を書けない理由を相手に伝えるために送るものです。特に慶事に関する内容を書くのは控えましょう。
どうしても相手に近況報告など伝えたい場合は、松の内(1月7日)以降に寒中見舞いを送ってみてはいかがでしょうか。このように基本さえおさえておけば、喪中はがきを書くこと自体はさほど難しくありません。
喪中はがきのデザイン
喪中はがきを作成する際は、華美なデザインは避けるようにしましょう。喪中はがきのデザインも多様化し、スタンダードな白黒以外のデザインも見受けられます。落ち着いた色合いを選べば、ご家族や故人が思い入れのあるデザインにしてもよいでしょう。
喪中はがきの文字の色は薄墨と黒の2種類ありますが、どちらで書いても失礼には当たりません。ただし、宛名面は黒を使用するのがマナーなので注意してください。
喪中はがきの作成方法
喪中はがきの作成方法として、主に以下の3つがあります。
(1)郵便局で弔事用のはがきを購入する
(2)市販の私製はがきを購入する
(3)喪中はがきの印刷サイトやお店で注文する
(1)の場合、切手部分に胡蝶蘭がデザインされたはがきを郵便局で購入しましょう。
(2)の場合も同様で、弔事用切手を使用する必要があります。弔事用切手は紫色の花が描かれたデザインで、郵便局の窓口で申し出ると購入できます。
12月後半に身内の不幸があった場合
12月後半に身内の不幸があった場合、喪中はがきは送らないほうが賢明でしょう。その時期は先方がすでに年賀状を投函している可能性があるため、相手に余計な気遣いをさせてしまうことになります。
喪中はがきを出す代わりに、年明けに寒中見舞いを送り、その中で年末に身内の不幸があったことを伝えるのがよいでしょう。
相手が喪中と知らずに年賀状を送ってしまった場合
「実は喪中だったのに、すでに相手に年賀状を送ってしまった」など、実際にこのようなことが起きた場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。
相手が喪中だとうっかり忘れていたり、年末に相手の親族に不幸があり喪中はがきが間に合わなかったなど、さまざまケースが考えられるでしょう。ここではそのような場合の対処法をいくつかご紹介いたします。
電話、手紙でお詫びの連絡をする
喪中だと後から知り、すでに年賀状を送ってしまった場合や、喪中はがきと年賀状が入れ違いになってしまった場合は、速やかに電話などでお詫びの連絡をしましょう。
最近だとメールで済ませようと思う方もいるかもしれませんが、相手によっては気分を害すこともあるかもしれません。電話などできちんと非礼のお詫びを伝える方が印象は良いです。
電話や手紙を送る際は、喪中だと知らなかったこと、失礼のお詫び、お悔やみの言葉は忘れないようにしましょう。
寒中見舞いでお詫びの言葉を送る
年末に相手に不幸があり、喪中はがきが間に合わないケースもあります。年賀状が相手に届いたあと、実は喪中だったと知ることもあるかもしれません。そのような場合は「寒中見舞い」にお詫びの言葉をいれて送りましょう。
寒中見舞いを出す期間は、松の内以降(1月7日)から節分(2月3日)までです。相手に届くタイミングも考え、1月末までにポストに投函しましょう。ギリギリになって送るよりも、喪中だと分かった時点で速やかに寒中見舞いを作成、投函するほうがベターです。
喪中見舞いでお詫びの言葉を送る
喪中だと後から知った場合や喪中だと忘れてしまっていた場合など、年内にどうしてもお詫びを伝えたい場合は、電話以外だと「喪中見舞い」を出すという方法も良いでしょう。
寒中見舞いだと、どうしても松の内(1月7日)以降に送ることになります。できるだけ早く、年内にお詫びの言葉を相手に伝えるなら喪中見舞いがおすすめです。
電話でも早くお詫びの言葉を伝えることができます。しかし「年明けを待たず年内のうちに、より丁寧な形で哀悼の意を伝えたい」という方は喪中見舞いを選択するのも一つの方法です。
喪中はがきをもらった場合
もし、自分自身に喪中はがきが届いた場合、どのように対応すればよいのでしょうか。
返信しない
遺族の気持ちに配慮し、こちらからの返信を控える場合もあります。
基本的には、喪中はがきへの返信はしなくてもよいとされています。
しかし相手によっては、喪中はがきに年賀状を希望する旨を書いている方もいます。そのような場合は、遠慮なく年賀状を出しても差し支えありません。どうしても気になる場合は、寒中見舞いや年始状で挨拶するのも良いでしょう。
年始状を送る
年始状とは「明けましておめでとうございます」や「迎春」など賀詞を使用しない年始の挨拶状です。おめでたい言葉の代わりに励ましの言葉などを添えることもあります。
年始状は、年賀状と同じく年始に届くよう送りましょう。ただし、年始状に年賀はがきを使用してはいけないので注意してください。
寒中見舞いを送る
喪中はがきへの返信として一般的なのは、寒中見舞いを送る方法です。松の内以降から立春までの期間(1月7日~2月3日)に相手に届くように送ります。
寒中見舞いの中で、喪中はがきをいただいたため年賀状を控えたことや、故人へのお悔やみの言葉を伝えるとよいでしょう。
喪中見舞いを送る
喪中はがきが届いたとき、すぐに哀悼の意を伝えたい場合は、喪中見舞いを送りましょう。喪中見舞いは年内に届くように投函します。近年は、喪中見舞いと一緒に線香などを送る方も増えています。
まとめ
大切な人、関係の深かった人が亡くなったとき、お通夜やお葬式、四十九日の法事、遺品の整理、必要があれば喪中はがきの準備など、親族にはやらなくてはいけないことがたくさんあります。しかし、喪中のマナーよりも大切なのは故人を悼む心です。だからこそ、喪中はがきなど早めに手配できることは済ませてしまい、ゆっくりと故人との優しい思い出を偲ぶ時間を確保してください。
関連コンテンツ